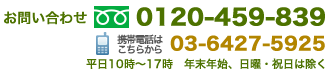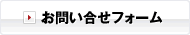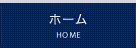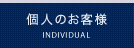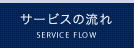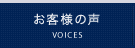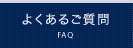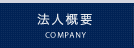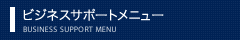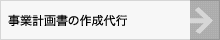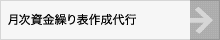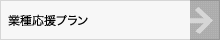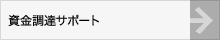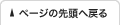報酬・サービス等に関するご質問
- ライブラ税理士法人は、どんなことしてくれるの?
-
税理士の提供するサービスは申告書作成だけではありません。
もちろん、税金・会計に関する事が中心ですが、ほかにもさまざまな業務のサポートを行っています。
たとえば、- 事業計画書の作成代行
- 月次資金繰り表作成代行
- 業種応援プラン
- 資金調達サポート
- 新規起業支援、相談
- 事業承継のシミュレーション
- 給与計算
- 社長個人の所得税の申告・相談からライフプランニング
などです。
今では、企業をとりまく様々な問題に対処すべく、税理士のサービス範囲は拡大しています。 - 税理士の料金ってどうなっているの?
-
同業と比較して決定するのが一般的です。
月額サービス報酬は、原則として「資本金」と「年間売上高」及び「訪問回数」により決定致します。
まずは、お客様の状況やご要望をしっかりとお聞きし、お客様にぴったりのコースをご提案致します。
最低料金となるようアドバイスさせていただきます。 - 起業しましたが、経理の仕方がわかりません。
-
起業されてすぐの社長は営業に専念されることをお勧めします。
当税理士法人では、領収書貼り等すべての記帳代行をお受けすることが可能です。
基本的には、当税理士法人のお客様は記帳代行を含めてサービスをご提供しております。
自社で処理するべきか、アウトソーシングする方が良いかは、必要に応じて当税理士法人よりアドバイスさせていただきます。 - 税務会計顧問の料金はいくらからですか?
-
月額6,800円(税抜)からとなっております。
月額サービス報酬は、原則として「資本金」と「年間売上高」及び「訪問回数」により決定致します。
まずは、お客様の状況やご要望をしっかりとお聞きし、お客様にぴったりのコースをご提案致します。
最も低料金となるようアドバイスさせていただきます。 - 月次サービスは不要で、決算だけをお願いできますか?
-
できます。決算業務のみや年末調整業務のみでもお受けしております。
詳しくは「年一決算」をご覧ください。 - 報酬の支払方法を教えてください。
-
毎月の顧問料は、お客様の手を煩わせることのないように翌月分を 当月28日にお客様の銀行口座より自動振替サービスによりにお支払いいただくことを原則としております。
決算料及びその他のスポット報酬については業務完了日を報酬発生の日として、翌月末日までにお振込をお願いしております。
(毎月の顧問料に加算させていただき自動振替にさせていただくことも可能です) - セカンドオピニオンとして依頼できますか?
-
当税理士法人ではセカンドオピニオンにも対応しております。
法人税、所得税、相続税、贈与税のことなど何でもご相談ください。
税理士が対応させていただきます。
法人向けサービスに関するご質問
- 節税対策はできますか?
-
もちろん、できます。
当税理士法人では節税は納税者の権利と考えております。
決算月の3ヵ月前に「予測決算報告書」を作成し、黒字、赤字の予測と節税の提案を行います。 - 会計ソフトを導入したいけどどうすればいいですか?
-
弥生会計をお勧めします。
当税理士法人に変更いただいた場合には特価で弥生会計を販売させて頂きます。
また、導入サポートも行っておりますのでご相談ください。 - 顧問契約の場合、どの程度訪問してくれるのですか?
-
3ヵ月に1回の訪問を基本としております。
お客様のご要望により、訪問の回数を毎月や2ヵ月に一度など調整することも可能です。 - 税務調査の立会いはしてもらえますか?
-
当税理士法人では経験豊富な税理士が税務調査の立会い業務を行っています。
税務調査では税務職員が納税者から事情を確認したり、帳簿や書類を調査します。
税務調査の立会いとは、税法の正しい知識と経験を身につけた税理士がその場所に出向いて一緒に説明したり、代って答弁したりすることをいいます。 そして、税務調査の結果は立会いをする税理士によって大きく異なります。税務調査の立会いは経験豊富な当税理士法人におまかせください!
- 売上のない(1000万円以下)会社でも対応していますか?
-
もちろん、大歓迎です。
当税理士法人のクライアントは、主として中小企業様や個人事業主の方です。
会社の規模に関係なく、お客様第一主義の精神で当税理士法人のサービスを提供させていただきます。
お気軽にお問合せください。 - 融資や資金繰りの相談はできますか?
-
はい、行なっております。
当税理士法人では、提携・協力金融機関と連携しております。 まずは、「資金繰り表作成サービス」をご参考下さい。
- 業歴が浅く、できるだけコストを抑えたいのですが、訪問回数が少ないプランを選択することに不安があるのですが?
-
当税理士法人では最低毎月一回は顔を合わせての「ミーティング」を推奨しております。
訪問回数が少ないプランでも、訪問のない月は、当税理士法人にお越しいただいての「月例ミーティング」をお勧め致します。 当税理士法人にお越しいただいてのミーティングやご相談は無料とさせていただいております。
- 年度の途中から変更することはできますか?
-
はい、行なっております。
過去の申告書、総勘定元帳を見れば処理は把握できますので、変更前後の税理士の間で引継ぎをする必要もありませんし、年度の途中からでも問題なく変更することが可能です
ただし、引継ぎができれば、スムーズに業務を遂行できます。 - 変更前後の税理士の間で関係が気まずくなったりしませんか?
-
そのようなことはございません。
同じ税理士業界に身をおいていても、税理士の数は相当多いですし、 事務所の所在する区が違うと、税理士間での交流はほとん どありません。
また、変更前の税理士に何も言わなければ、どの税理士に代わったかということもわかりませんのでご安心ください。 - 今の税理士をどうやって断ればいいですか?長い付き合いですので言いづらいです。
-
上手な断り方をお教えしますので一度ご連絡ください。
個人向けサービスに関するご質問
確定申告関連
- 不動産を売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?
-
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。 申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。なお、各税務署で申告書の書き方についての無料相談を実施しています。
- 投資用マンションを購入したけど、確定申告は必要なのでしょうか。
-
確定申告は必ず行なってください。マンションを所有し、第三者に賃貸した場合、不動産所得が発生しますので、 他の所得と不動産所得を合わせて確定申告をすることになります。その際、建物の減価償却費、 住宅ローンの利息などの必要経費が認められ不動産所得が赤字になった場合、税務効果があれば、この申告によって確定させる必要があります。
生前贈与関連
- どうすれば贈与が発生するのですか。
-
民法上贈与は贈与者側の「あげる」という意思表示と受贈者側の「もらう」という意思表示があって初めて成立します。 従って一方的に「あげた」という行為だけでも成立しませんし、逆に貰ったという一方的な行為だけでも成立しません。
<参考>民法第549条「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりてその効力を生ず
- いくら以上贈与すると税金がかかるのですか?
-
個人から年間110万円以上の財産を貰った場合、申告及び納税が必要となります。 この贈与税がかからない限度枠110万円の事を基礎控除と言いますがこれは受贈者1人に対しての年間での枠です。 従って、同一年において父から110万円、母から110万円貰った場合、年間合計で220万円貰ったこととなるので申告及び納税が必要となります。
- 110万円以下の贈与の場合申告は不要?
-
受贈財産の課税価格が110万円以下の場合、確かに申告要件はありませんが申告してはダメというわけでもありません。 贈与の事実を後にまでより明確にしておくためにも納税額ゼロの内容で申告しておくに越した事はありません。
- 贈与税の税率について教えて下さい。
-
次の速算表をご利用ください。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円以下 10% ? 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円超 50% 225万円 - 不動産を贈与する場合の評価額は?
-
贈与税の計算をする場合の受贈財産の評価額は相続税評価額によります。 具体的には土地であれば路線価(国税庁HP参照http://www.rosenka.nta.go.jp/)によって、 建物であれば固定資産税評価額によって評価します。ただし、他人に貸している土地や建物については他人の権利分評価額が低くなります。
※不動産を贈与した場合、受贈者には不動産取得税や登録免許税がかかります。
- 贈与税の税率は高いようですがなぜ生前贈与が節税になるのですか。
-
いま生前贈与をすることにより将来減少する相続税(リターン)といま納付しなければならない贈与税(コスト)との差額が節税額となります。 この場合リターンは相続税の限界税率を用いて、コストは贈与税の実行税率を用いて計算すると良いでしょう。
- 現金贈与であっても贈与契約書は作成したほうが良いですか?
-
生前贈与加算の規定を考えても贈与のあった日を明確にするため作成するのがベターです。 しかし本当に重要なのは対税務署ではなく対共同相続人の為の作成です。後の相続の際に被相続人に本当に贈与の意思があったのか (勝手に財産を移転したのではないのか)争うケースが多いので意思を証明できる贈与契約書の作成が肝要かと考えられます。
- 名義預金とみなされない為の贈与の方法は?
-
子名義の預金通帳に、親や祖父母が毎年振込や預け入れにより入金するという方法で贈与しているケースがよくあります。 しかし、一定の要件を満たしていない場合、名義を借りているだけで実質の所有者は親や祖父母本人とみなされ贈与が不成立とされる税務調査結果が増加しています。 せっかくの贈与を有効とするには少なくとも通帳の印鑑は受贈者のものを使用し、通帳と共に受贈者に預けておくのが良いでしょう。また贈与契約書を作成しておけばより贈与の事実をはっきりと証明出来ると考えられます。
- 生前贈与しても一定の贈与財産の額は相続税の計算上相続財産に戻されると聞きました。贈与者の健康状態が思わしくない場合生前贈与を実行しても意味がないでしょうか?
-
贈与者とあなたとの関係が被相続人⇔相続人である場合、又は、相続人ではないが遺言により財産を受け取る場合は、 当該相続の開始の日からさかのぼって3年以内の財産の贈与については生前贈与加算の適用を受け節税効果は実質無効化されてしまいます。 逆に言えば3年と一日経過した贈与については将来の相続財産から抜けていきますのでやはり思い立った時にすぐに贈与を実行するに越した事はありません。 毎年1月中には贈与を済ませておくのがベターです。なお、贈与者とあなたとの関係が上記以外の場合、 生前贈与加算の規定の適用はありませんので贈与があった時点で早速将来の相続財産から抜けていく事になります。
- 精算課税贈与をしても資産家にとっては節税にならないと聞きましたが本当ですか?
-
生前贈与により節税スキームを行う場合、通常は毎年の一般贈与により少しずつ財産を移転してく方法を採ります。 しかし、評価額は大きいのだが収益を生み出す資産(貸し店舗や貸しアパート等)を生前に贈与して今後の収益の帰属を変える事に より将来の相続税を節税する方法もあります。どちらの方法を使うかはケースバイケースと考えられます。
- 贈与を受けた年中に贈与者が死亡しました。申告・納税はどうすればよいのでしょうか?
-
贈与者とあなたとの関係が被相続人⇔相続人である場合、又は、相続人ではないが遺言により財産を受け取る場合は、 贈与を受けた財産は相続財産に戻され、これをあなたは相続で取得したものとして相続税の計算が行われます。 (贈与申告は不要)なお、贈与者とあなたとの関係が上記以外の場合、通常どおり贈与税の申告及び納税が必要となります。
- 贈与税の配偶者控除の規定を適用すれば節税になると聞きましたが本当ですか?
-
婚姻期間20年以上の夫婦間であれば居住用財産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与しても2,000万円まで非課税という規定があります。 ただし、こちらは同一世代間での財産の移転になりますので、二次相続を考えると受贈者固有の財産額の多寡や年齢バランスなどを 考慮しないと殆ど節税にならず経費倒れになる場合がありますので実行にあたっては注意が必要です。
- 離婚時の財産分与により取得した財産には贈与税は掛かるのですか?
-
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、 慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものだからです。ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
- 父の成年後見人をしています。父の財産を私や兄弟に贈与で移転することは出来ますか?
-
成年後見人となっているということは、被成年後見人であるお父さんは意思判断能力がないということになります。 成年後見人は基本的に本人の財産を本人のためだけに使用することしかできないので、 生前贈与などをすることは不当に被後見人の財産を減少させる行為として「業務上横領」になってしまう可能性もあり注意が必要です。
相続税申告関連
- 顧問税理士がいるのだけど。
-
所得税や法人税については、そのまま従前の税理士先生にお任せして、 相続税申告のみを弊法人にご依頼いただくことも可能です。税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。 例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。 日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続や資産税について専門知識を有する税理士は少数です。 あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約6万5千人、1年間の申告件数は約4万8千件あります。 この申告件数÷税理士登録者数=0.75件となるように1年間で相続の申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。 申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。 このような現状から税金が事後的に還付されることがあるのです。
- 異なる相続人ごとに他の税理士にお願いすることはできますか。
-
はい、可能です。但し、争いの無いような一般的な場合は、コスト面において同一の税理士にお願いされる方が良いと思います。
- 相続税申告を資料の郵送のみで依頼することは可能でしょうか?
-
はい、可能です。地方にお住まいの方でも、弊法人では、必要資料マニュアルを用意しているため、 必要資料をご郵送頂き、電話やメール等でコミュニケーションをとることができれば、 日本全国どちらにお住まいの方でも、ご依頼頂くことが可能です。
- 資料の取り寄せ等のアドバイスはもらえますか。
-
資料取り寄せに関する手続きガイドを進呈(無料)しておりますし、 また取り寄せ方法等で分からないことがあればいつでもアドバイスを差し上げています。
- 資料取り寄せや遺産調査等のサービスを部分的にお願いすることは可能ですか。
-
可能です。(但し、所定の手数料を別途頂戴いたします。)
- 準確定申告も行っていただけますか。
-
はい。実行の際は別途報酬を見積もらせて頂きます。
- 納税資金がないのですが。
-
別途報酬がかかりますが、延納や物納のご相談にも応じます。
- 相続税の還付を受けられることはありますか?
-
一度支払った相続税は平均で500万円戻ってくると言われています。過去5年以内に申告済みの相続税については、 還付されるケースがあります。税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。 例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。 日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税について専門知識を有する税理士は少数です。 相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。 このような背景から誤って申告した相続税が事後的に還付されるケースが多くあります。
- ハイパーローコストプランは何故低価格なのですか?
-
お客様ご自身で行っていただけることはご自身で行っていただき、また当税理士法人の作業負担が少ない条件に当てはまるお客様に限りハイパーローコストプランを特別にご用意させて頂いております。
生前対策関連
- 生前贈与(相続時精算課税贈与、暦年贈与)、親族間の売買なども行っていただけますか。
-
はい。対策レポート作成時に見積もり等も含めてご提案させていただきます。また、対策レポートの作成なしに生前贈与のみを行うことも可能です。
- 銀行等の金融機関が提案する生前対策との違いは?
-
銀行が提供する生前対策は、やはり主に資金融資を前提としたものになる傾向が強いです。 借入を行わなくてもできる生前対策はたくさんあります。お客様のそれぞれの状況に応じて最適なご提案を行いますので、コスト(支払利息や手数料)を抑えた対策の実行も可能です。
- 生命保険の活用は重要ですか?
-
生命保険の活用は最も基本的な生前対策です。特定の方(たとえば長男)に先祖からの土地を相続させるためや、相続税の資金を残すために生命保険の活用も大事です。
- 成年後見制度とは?
-
年をとると、認知症や知的障害・精神障害のことも考えなければなりません。現在の能力や財産を生かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し、支援する制度です。 現在の判断能力に問題はないが、将来に備えて契約する「任意後見制度」や判断能力を欠くに至り、家庭裁判所への申し立てにより後見人などを選任してもらう「法定後見制度(後見、補佐、補助)」とがあります。一人暮らしの方やお子様が遠方の方などぜひご利用ください。
遺言関連
- 遺言書は作成しておくべきでしょうか
-
遺言書を作成する必要性はわかっていても、作成を先送りしている方は多いです。しかし、不動産や未公開株などの相続財産が大半を占めるケースでは、法定相続分で分けるのはそもそも難しいですし、相続税が発生する場合には納税資金が確保できず、マイホームを処分することになりかねません。また、事実婚の方や生前にお世話になった方等の法定相続分がない方に相続させるには、遺言書の作成は不可欠となります。
- 遺言書は自筆で作成すればよいでしょうか
-
遺言書の作成方法としては、主に自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。自筆証書遺言は個人が自筆で作成するものであり、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言書をいいます。自筆証書遺言だと、本人の死後、遺言書を開封して相続手続きを開始するには、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。この検認には1カ月~2カ月かかり、その間は遺族はすぐに預貯金等を引き出せなくなります。また、検認が終わったあとでも、遺言書の形式不備等により内容が法的に無効になる可能性もあります。その点、公正証書遺言だと、家庭裁判所の検認が不要なため、相続発生後、遺族はすぐに相続手続きを開始することができます。また、公証役場で保管されるため、紛失や捏造のリスクもなく、形式面で問題が生じることもありません。
- 遺言書の作成支援等もやっていただけますか?
-
はい。公正証書遺言及び自筆証書遺言の作成支援も行っております。書類作成のプロである行政書士が全面的に支援致します。
事業承継関連
- 事業承継対策はいつからすべきでしょうか?
-
事業承継を円滑に行うためには、多岐にわたる事柄に取り組まなければならないため、事業承継は時間がかかります(おおよそ3年~10年)。そこで、事業承継対策は、なるべく早く取り掛かることが重要です。
- 事業承継とは、何を承継させていけばよいのでしょうか?
-
事業承継の本質は、後継者に対して、会社経営をしていくための基盤となる株式や会社経営のために必要な事業用資産を引き継ぐ財産承継の側面のほか、経営者としての立場や権限、責任といった経営者としての地位を引き継ぐ経営承継の側面があります。株式や土地・建物といった資産のほかに、経営者としての立場や権限、取引先や従業員との関係や経営理念なども引き継ぐ必要があります
- 事業承継対策は誰に相談したらよいでしょうか?
-
事業承継円滑に行うためには、後継者の選定、後継者候補や幹部人材の教育、関係者から信頼関係を得ること、法務対策や税務対策などさまざまな事項の検討を行うことが必要です。法務対策は弁護士、税金対策は税理士、登記関係は司法書士、教育はコンサルタントなど相談事項に応じて、専門家に相談することになります。
- 親族に後継者がいない場合、どうしたらよいでしょうか?
-
子息・子女、あるいは、跡を継ぐ可能性のある後継者候補が親族内にいないときは、役員・従業員への承継、あるいはM&Aを活用した事業承継を中心に検討することとなります。この場合、役員・従業員等への承継をまず検討すべきですが、社内の人間に事業を承継するために必要な、後継者の人選や資金調達がうまくいかない場合には、社内以外の第三者にM&Aを活用して承継することを検討することになります。
- 借入金が大きくて後継者に事業承継できないのですが、どうしたらよいでしょう。
-
借入金の大きいままで承継をすると、後継者まで共倒れになる可能性があるので、再建の見込みがある場合には、再建計画を立てて事業の再生を行うなかで、借入金を圧縮して財務を健全化させたうえで、後継者に事業を承継することになります。なお、事業再生の一環として金融機関等から債務免除を受けると現経営者は経営責任を明確にするという意味で退任させられることが多いので、事業再生に着手する前までに後継者による事業戦略の構築や組織の適正化といった新経営体制を確立するほか、不採算事業からの撤退や経費の削減など収益構造の見直しをしておくことが重要です。
- 廃業して会社を清算するとしたら、どのようになるのでしょうか?
-
自主的に解散して廃業する場合には、私的合意によって行われる任意清算と法律で定められた裁判上の手続によって行われる法的清算があります。廃業の意思を決定したら、従業員や取引関係者等の理解を得たうえで、株主総会で解散の決議を行って清算手続に入ります。債権の取立てを行い、金銭以外の財産を処分し金銭に換えたあと、債務の支払をすることで会社の資産と負債を整理します。整理の結果、清算所得が生じていれば税金を納付し、残余財産を株主に分配したのち、清算決了登記をすれば清算手続は終了します。もっとも、債権の取立てや財産の処分による金銭への換価が簿価を大きく下回ることも多く、債務超過の疑いが出てきた場合には、清算人は裁判所に対して特別清算の申立をしなければならなくなります。
営業時間・お問い合わせに関するご質問
- 地方に住んでいるのですが、近所に相続に強い税理士さんがいません。このような場合に、資料の郵送のみで依頼することは可能でしょうか?
-
原則として、全国のお客様に対応しております。
はい、可能です。地方にお住まいの方でも、当税理士法人では、必要資料準備ガイド等の申告のために必要な業務ツールが充実しておりますので、 必要資料をご郵送頂き、電話やメール等でコミュニケーションをとることができれば、 日本全国どちらにお住まいの方でも、ご依頼頂くことが可能です。
- メールで質問に答えてもらえますか?
-
お問い合わせフォームよりご相談いただければ、できるだけ早くお答えします。
また、基本的に相談は無料です。特に複雑な計算や判断が必要な事案などは、別途料金が発生する場合もございます。
そのような場合には、事前にお伝えしますので、お気軽にご質問ください。 - 営業日時、問い合わせの時間を教えてください。
-
当税理士法人の営業日時は、月曜日~金曜日の午前9時30分~午後6時までです。
土日祝日は休業とさせていただいております。
また、メールでのお問合せは年中無休24時間受付中です。
原則として送信後翌営業日以内に返信させていただきます。
お問合せフォームより、どうぞお気軽にお問合せください。 - 無料相談の内容を詳しく教えてください。
-
当税理士法人では初回の相談料を無料とさせていただいております。(30分程度)
お電話か、お問合せフォームで無料相談のご予約をお願い致します。
皆さまからの疑問やご質問に対して、税理士が個別にご相談を承ります。
会社設立や税務全般、相続や贈与、マイホームの税金のことなど、お気軽にご相談ください。 - 相談内容・財務内容が外部に漏れたりしませんか?
-
お客様の情報を第三者に漏らしたりすることは一切ございません。
税理士には、法律による守秘義務が課せられており、業務の過程で知りえた相談者、依頼者の情報を漏洩してはならないとされています。 違反した場合には2年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。(税理士法第60条)
どんな内容でも、安心してご相談ください。
- 依頼したいのですが、どうすれば良いですか?
-
まずは、お電話か、お問合せフォームでお問い合わせ下さい。
お客様の解決したい問題点をお伺いし、当税理士法人のサービス内容をご案内させていただきます。 その後、ご面談させていただきます。
詳しいご相談、サービス内容のご説明をさせていただきますので、ご納得いただけましたらご契約ください。